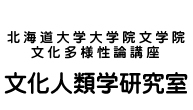- HOME
- 2018年度博士論文要旨(歴史文化論講座)
石原 真衣
<沈黙の>オートエスノグラフィー
―「サイレントアイヌ」におけるサバルタン化のプロセスとポストコロニアル状況 ―
1586 年、スイスのレンヴァルト・シサットが『日本諸島実記』において、「蛮人」としてアイヌを紹介
した。その後、アイヌはヨーロッパで知られるようになり、アイヌは良き野蛮人であったり、動物に比
されたり、世界でもっとも原始的な文化をもつとされたり、抑圧された「死にゆく種族」とされたり、
まわりまわって「エコロジー的に高貴な野蛮人」として復活したりした。アイヌはずっと、「歴史の他者」
として存在してきたのである。
これまで、現代アイヌ民族に関する調査や研究は、社会学的視点から多数派である和人との関係性を
考察した研究、「普通」のアイヌの人びとの語りに着目した研究や、アイヌ民族の世代や地域差による多
様性に着目した調査がある。これらの研究は、アイヌ民族の声を重視し、差別や経済格差および学歴の
低水準などの現代的な問題点や、アイヌ民族の成員が逞しく民族性を確立しようとする姿を明らかにし
た。しかし、北海道ウタリ協会と無関係もしくは疎遠である人々を調査対象にすることは困難であり、
近年行われている調査の対象が限定的であることは否めない。アイヌ民族実態調査における過少申告の
問題もある。そこには、他者を対象とする調査や研究が到達できない〈アイヌ〉の断層がある。
本論は、その断層における現象の一つである、「サイレント・アイヌ」の実態に迫る試みである。アイ
ヌの出自を公の場で明らかにしない人々を指す用語として「隠れアイヌ」あるいは「表にでないアイヌ」
という言葉がある。アイヌ同士の集まりや、研究者などがアイヌの状況について話す際に、使用されて
いる。しかし、これらの言葉では、出自について沈黙せざるを得ない社会的要因があり、語りたくとも
語れない、自己の存在がわからず何を語ればよいのかわからないという状況を明確に示すことはできな
い。よって本論では、アイヌの出自を持ちながらも、歴史や文化を失い、自己が何かわからなくなり沈
黙している人々を指す用語として「サイレント・アイヌ」を提唱したい。しかし、当事者が出自につい
て公にしないが、アイヌ民族としての意識やアイデンティティを持っている場合もある。このような人々
を本論では、「サイレント・アイヌ」とは捉えない。本論では、第6章と第7章において、「サイレント・
アイヌ」という概念の詳細な分析を行う。
本論は、いかに「サイレント・アイヌ」が、ポストコロニアルな歴史の中で、自己の歴史や言葉を失
い、サバルタン化したかという問いに、ポストモダンの人類学的理論、ポストコロニアル論およびサバ
ルタン論と、イギリス社会人類学における分類理論と、そこから派生した境界理論から接近する試みで
ある。具体的な事例として、ポストコロニアルな歴史と、そこからつらなる現在という時制において、
不可視な存在となっている「私」の家族史とオートエスノグラフィーを描き、通時的な歴史と「私」を
取り巻く共時的な社会構造を照らし出すことを目的とする。
海外諸国において、先住民研究の最重要項目の一つである「脱植民地化」というキーワードが、なぜ必要かというと、先住民の置かれている現在の状況が通時的・共時的な植民地主義に影響されているという前提を共有するためである。本論ではこのような視点を導入し、なぜ、アイヌの出自を持つ「私」が、自己の存在が何であるのかわからなくなり、透明人間と化して、声を失うのかについて、エスニシティやアイデンティティといった視点からではなく、植民地主義的な過去からつらなる現在における社会構造といった視点から分析する。
サバルタン論の「語る」と「聴く」という発話に関する議論を批判的に継承し、発展させる試みとして、いかに、ある主体が声を失っていくのかというサバルタン化のプロセスについて思索する。ガヤトリ・スピヴァクは、サバルタンとは社会構造にアクセスできない主体であると述べた。スピヴァクが正しく述べるように、サバルタンを取り巻く問題とは、雑種性 ハイブリディティのような曖昧なアイデンティティの問題で はなく、サバルタンが生きる社会構造の問題である。なぜ、「サイレント・アイヌ」が沈黙するかという問いに答えるために、社会構造について思索することが有効である。
「サイレント・アイヌ」が沈黙する背景について思索するために、人類学の基礎ともなっており、人間の認識や知覚に大きく影響する「分類」に着目する。本来、自然とは文節のない 混沌 カオス であり、そこに 切れ目を入れる―-つまり分類する――ことで、人間は世界を見ることができる。しかし、本来文節がな
い自然に切れ目を入れることは、そのどちらともいえないものが出現することでもある。世界には、分類しえない存在やものが常にあり、それは穢れや混沌であると考えられ、人々に危険を及ぼすと考えられてきた。
人類学者ロバート・エジャトンは、東アフリカの Pokot におけるインターセックスについて論じ、分類できない存在をその社会がどう扱うかについて考察することは、その社会にとって「何が自然で、正しいか」という視点を明らかにすることを述べた。また、メアリ・ダグラスは、双生児がかつて出産に際して殺されていた事例について述べ、異例なるものが、解釈が行われたり、物理的に処理されたりする様子について研究した。その結果によって、不浄や汚物はある体系を維持するために、そこに包含してはならないものであることを述べた。一方で、エジャトンの研究は、アメリカのナバホでは、インターセックスとは、富や繁栄をもたらすものと考えられているが、Pokot では、多くの場合出生時に殺されてしまい、「完全な人間」になれない存在として扱われることを示している。分類できない存在を排除するか、新たな力をもたらす源であると考えるかは、社会によって異なるのである。
「サイレント・アイヌ」とは、歴史と文化との繋がりを失い、自己の存在が何かわからなくなっている存在である。言い換えれば、従来の分類枠組みで捉えることが困難な存在であるといえるだろう。当事者を含む社会全体が、このような存在をどのように認識しているかについて分析することは重要である。分類不可能な主体が、声を発しようとするとき――つまり、社会構造にアクセスしようとするとき――、「話す」と「聴く」をいう言語行為を阻むものの一つが、以上で述べた社会における分類システムにあると考える。分類できないものが、ある体系を維持するために、排除すべき対象として扱われる社会構造においては、従来の分類枠組みに当てはまらない主体が声を発することは難しい。
スピヴァクのサバルタン論を批判的に参照することの利点は、ある主体の沈黙と社会構造を結び付けて思索することが可能になる点である。よって、「サイレント・アイヌ」の沈黙の背景を探るために、「サイレント・アイヌ」がアクセスできない社会構造について分析する。これまで、文化人類学をはじめとする人文学では、他者を表象することにおける政治的力学ついて、議論が重ねられてきた。しかしレナート・ロサルドが指摘したように、知識の構築とは、パースペクティブによって可能となり、そしてそれが故に制約を受ける。そうであれば、研究する側も「位置づけされた主体」であり、その主体が他者表象を行うことには、常に不可視の領域――〈断層〉――がその表象から排除される、あるいは誤認として表象され続ける、という可能性を持つ。本論では、このような「研究する側/研究される側」という二分法による他者表象が抱える構造的問題を乗り越え、この<断層>を、他者にも知覚可能にする一つの方法論として、オートエスノグラフィーを位置付けたい。
オートエスノグラフィーは、自伝的民族誌と訳すことが可能だろう。従来の客観的・中立的な解釈を重要視する研究方法に対し、個人的経験の社会的・文化的諸側面へと再帰的に迫ることが、オートエスノグラフィーによって可能となる。これまで、病いや障がいなどの当事者によってオートエスノグラフィー研究が重ねられてきた。従来の研究手法では明らかにすることができなかった「私」を研究対象とするときに、オートエスノグラフィーを方法論として採用することは有効である。しかし、「私」を研究する上で、最大の問題点のひとつは、「私」が何の当事者であるのか分からないことであった。「私」は従来の枠組みでは捉えることが困難な存在なのである。よって、オートエスノグラフィーを描くために、北海道浦河町のべてるの家ではじまり、近年様々な拡がりをみせている当事者研究に注目する。
上野千鶴子は、当事者とは第一次的なニーズの帰属する主体であり、「ニーズの主人公」であると述べた。さらに「当事者であること」と「当事者になること」を区別した。ニーズや当事者は、常に顕在化しているのではなく、様々なプロセスを経て、ニーズが明らかになり、人は当事者になるである。当事者研究の特色の一つは、当事者がもつニーズを明らかにすることによって、研究する主体を当事者化である。「私」は、歴史と現在という社会空間をさまよう透明人間である。自己の存在を見ることができず、他者からも見えていない。そのような「私」が、当事者として研究をする際に、以上のような当事者研究の視点が参考になる。
不可視になっている領域、つまりは当事者以外には問題とされない領域において、あるニーズを抱え得る人々が当事者になって居ない場合、それは研究対象にならない。この意味で、「研究する側」が持つ選択可能性は、実は限定されていると指摘することができる。「研究する側」も、一定程度の限定性の下における選択によって行為しているにすぎない。問題そのものが焦点化されておらず、ニーズが何であるかについても明確ではない場合、その当事者や問題は透明で不可視であるということになる。自己が抱える問題や痛みを始点として、そこからニーズを明らかにして、自己を当事者として主体化するのが、当事者研究である。この当事者概念を取り入れ、当事者とニーズは不可分であるとするならば、アイヌ民族と「私」は異なる当事者であることになる。ほとんどのアイヌ民族と表象される人々は、アイヌ文化と自らの存在をほぼ不可分と捉え、その復興や継承を可能にすることをニーズとしている。あるいは、福祉的な側面から言えば、社会的格差の是正を求めている。一方で、「私」は、文化の継承や社会的格差の是正のみでは語り得ない、他のニーズを携えているのではなかろうか。
まずは物語によって、「私」のニーズを明らかにする。そのことによって、自己が何の当事者であるのかが明らかになり、それをオートエスノグラフィーと掛け合わせて、社会的・文化的諸側面へと再帰的に迫ることが可能となる。オートエスノグラフィーと当事者研究は、他者表象を目的にするのではなく、自己表象である側面が大きいため、他者表象における政治的力学といった視点は持ちにくい。しかし、自己表象であっても、他者の声を奪う可能性を秘めているだろう。よって、本論では、文化人類学的な他者表象における政治的力学に関する議論を踏まえて、オートエスノグラフィーと当事者研究という方法論を刷新したい。
第4章では、近現代のアイヌ民族の自己表象について、主として北海道アイヌ協会による媒体から確認する。アイヌ民族は、明治の開拓使設置以降、臣民化を志向し、第二次世界大戦後は、GHQ などとの接触の後、異民族であると主張を始め、世界的なブラックパワーや市民権運動に後押しされる形で、「少数民族」、「先住民族」として頭角を現した。アイヌ民族が「先住民」という自画像をもつ現在、アイヌ民族を取り巻くアクターは、国内外の多岐にわたる。先住民に関する議論を主導してきた国連などの国際機関や、国内の行政が、「アイヌ民族」というイメージを構築する行為主体性を発揮している。
第5章と第6章では、第4章までの議論を踏まえ、私の家族4世代の物語を歴史化する。曽祖母のつるは、平取町荷負にあったポピポイコタンで生きた。母語をアイヌ語とし、唇の周りには入れ墨を施していた。コタンでは、ほとんどの住人がアイヌであったため、アイヌの伝統的な暮らしをしていたが、コタンの外に出るときは、差別的な眼差しを回避することはできなかった。祖母のツヤコは、ポピポイコタンで生まれ、8 歳のときに、和人の農家で奉公を始める。和人との圧倒的な民族的・経済的格差を目撃したツヤコは、生涯、徹底的にアイヌの文化を排除し、和人との結婚に固執し、労働に生きた。文化や血を否定しながら生きざるを得なかったツヤコだったが、逞しく日本社会を生き抜き、生涯誰も恨まずに、明るく朗らかに暮らした。母のイツ子は、平取町本町で生まれ、15 歳までそこで暮らした。『アヌタリアイヌ―われら人間』の刊行に携わり、人間とは、民族とは何かを生涯問い続ける。人種的にアイヌと位置付けられながらも、文化的にアイヌの側面を何一つ継承していないイツ子は、自己の存在について混乱し、葛藤した。イツ子は、ツヤコを心から敬愛しており、私にも、ツヤコの「血」であるアイヌの出自を受け入れることを望んだ。
12 歳のときに、祖母がアイヌであったことを母から聞かされた後、私は成人するまでアイヌの出自について他言しなかった。札幌生まれで札幌育ちであったため、アイヌの人に会ったことがなかったし、家族や親せきは決してアイヌという言葉すら発することがなかった。アメリカ留学を経て、英語や国際教育の教員となったが、なぜ、「私」という異文化について触れずに、海の向こうの西洋文化に対して異文化理解を説くのかについて、違和感を持ち、なぜアイヌの出自を持つことを沈黙しなければならないのかを明らかにするために、28 歳で北海道大学大学院に入学する。
大学入学後、突如私は、アイヌとして位置付けられる経験をした。私が「アイヌと思っていない」ことを告げると、「アイデンティティが揺らいでいる」あるいは、「アイヌであることを否定している」と言われた。そのことに違和感を覚え、語ることを試みるも、その声はいつも誤解されてきた。そして、私は再び沈黙した。なぜ、人々は、私の声を聴いているのに、私は誤解されるのか、なぜ、私はそこにいるのに、人々にその姿がみえていないのか、このような問いに答えるために、私は、「私」を研究する。公式なアイヌ民族の歴史によって描かれる人々とは、ルーツを共有しながらも、「サイレント・アイヌ」には、異なる物語がある。名もなき人々の物語を紡ぐことで、新たな分断を作るのではなく、互いが異なる生を紡いだ背景を探り、どちらか一方を光や影にすることを避けながら、新たな交差点を生み出す可能性を探りたい。
第7章の結論では、 「私」はなぜ透明人間で、なぜ、人々は「私」の語りを了承しないのかという問いに、家族の世代間における縦の分断、そして、そのことがもたらす他のアイヌとの間における横の分断、痛みや言葉の喪失と、社会構造における分類体系といった視点から、〈沈黙〉というポストコロニアル状況について述べる。この結論で述べられる視点は、アイヌの出自を持つ人々のみならず、社会の中で不可視化している様々な人々に関する今後の議論のための言葉を創造することを目指すものである。